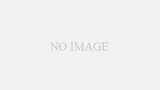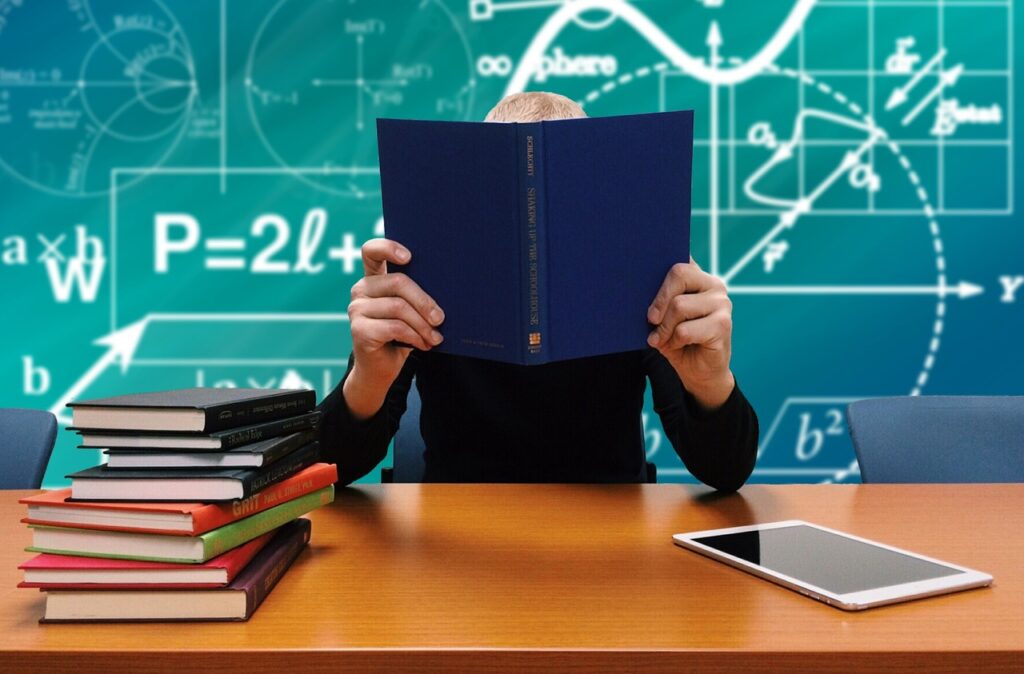
今の仕事を定年まで続け、退職後はのんびり過ごす。これで充実した人生を過ごしたと胸を張って言えますか?
実は、終身雇用、年功序列で定年まで1つの会社で働き、余生を楽しむという日本型の働き方は限界を迎えています。
なぜなら、人生100年時代の現在、60歳ーこれまでの定年ーから、多くの人に約40年もの時間が残されており、老後をのんびり過ごすだけでは満たされない充分すぎる時間が残されているからです。
いつまでも今のまま働き続けることに不安はあるけど、毎日仕事に追われていてやりたいことを探すには時間も十分とは言えません。
私も将来についてあれこれ想いを巡らせてみましたが、どうすればいいか答えを見つけられないまま、時間だけが過ぎていきました。
答えのない問に立ち向かっていると、私は消耗してしまいます。充実した人生を探してスタートしたはずなのに、消耗してしまうと言うのはなんだかチグハグです。
そこで、まず自由の土台の一つであるお金について勉強してみることにしました。
2年半で日商簿記(簿記)2級、ファイナシャルプランナー技能士(FP)2級、宅地建物取引士(宅建士)の3つの資格を取得しました。
このサイトでは、私の人生を楽しむ一歩目としてはじめた「お金の勉強」についてまとめています。社会人になって20年以上、勉強することから離れていた私の経験と継続できたコツなどをまとめます。
私の経験を参考に悩むより動きはじめてみませんか。
もくじ
- 【最初の一歩】決断力のない私が動き出すきっかけとして始めたお金の勉強
- 【悩むより行動】2年半で簿記2級、FP2級、宅建を取得
悩み続けて1年半・・・お金の勉強を始めることを決めました
【2年半でコンプリート】合格までのスケジュール|簿記2級、FP2級、宅建
- 記帳ルールを学ぶ簿記、正確な記憶定着が必要な宅建、暮らしのお金を学べるFP|3つを取得して感じた違い
簿記は世界共通の経済活動のルール。ビジネスにおけるお金の管理について総合的に学べます
宅建は不動産取引の専門家。専門分野を目指したい人にオススメ
FPは暮らしのお金のエキスパート
- 学習の難易度 宅建>簿記>FP|学習を終えた私の感じた体感
- 簿記→宅建→FPを受験して感じた学習のコツ|オススメの学習順序
【最初の一歩】決断力のない私が動き出すきっかけとして始めたお金の勉強
「悩んでも納得できる答えが見つからないときには、動き出してみよう。」
これが、3つの資格試験に挑戦しようと思ったきっかけでした。
私はやりたいことが見つけられないまま進学・就職し、社会人を20年ほど過ごしてきました。周囲の先輩や仲間たち、楽しくやりがいのある仕事に恵まれて、振り返れば充実した社会人20年を過ごしてきました。休日には、美味しいものを食べたり、旅をしたり、フットワークは軽い方なのですが、これといった特別な趣味があるわけではありませんでした。
しかし、人生の先輩たちの話を聞いたり、コロナ禍などを経て、どうやら今のまま毎日を過ごしても、一区切りと思っていた60歳の後に時間は十分すぎるほどに残されており、楽しく歳を重ねる自分を想像できなくなっていることに気づきました。
それから、本を読んだりネットサーフィンしてみたりあれこれ想いを巡らせてみたりしましたが、なかなか「こうすれば私のみらいは楽しいものになる!」という答えは見つけられませんでした。
今の暮らしを続けていれば、それなりに不自由なく過ごすことはできそうですが、将来への不安や何か分からないモヤモヤした気持ちが晴れそうにありません。
それでも、時間はどんどん過ぎていきました。
このまま悩んでいても納得できる答えは見つかりそうにないし、モヤモヤと過ごし続けるのは、逆に楽しく過ごしたいという目的から遠ざかっている気がして、とにかく何か行動してみることにしました。
直接的ではないにしろ仕事を続けるにも、転職などをするにしても役立ちそうで、これからを考える上でも大切なマネーリテラシーの向上を目指して、簿記、FP、宅建の3つの資格にチャレンジすることにしました。
どれもこれまで関わりのなかった資格なので、ほぼゼロからのチャレンジでした。
それでも、学ぶ楽しさや試験前の焦り、合格発表前の緊張感、そして達成感を体験することができました。もちろん、知識を得たことは、これからを考える上での武器にもなります。
もし同じように、何かを変えたいけれどどうしていいか分からない、答えが見つからないというなら、まずは動き始めてみるというチャレンジからスタートしませんか。
(LNK)3つの資格以外にマネーリテラシーを高めるためにやっていることはこちらのリンクをご覧ください
【悩むより行動】2年半で簿記2級、FP2級、宅建を取得
悩み続けて1年半・・・お金の勉強を始めることを決めました
実は答えの見つからないモヤモヤした気持ちを抱えてから、勉強を始めるまで1年半もかかりました。過去を振り返ってみたり自分との対話を続けるうちに、私は、やりたいことややるべきことがはっきりしていないと、不安からか精神的に滅入ってしまうことに気づきました。
みらいを楽しむことを目指していたはずなのに、その前に疲れてしまっては、本末転倒だと思い、まず簿記を勉強することにしました。
簿記の勉強が一区切りしたタイミングで、友人が宅建士の勉強していることを知り、このきっかけを逃すまいと宅建士の勉強をはじめ、最後にFPを取得しました。期間としては2年半です。
【2年半でコンプリート】合格までのスケジュール|簿記2級、FP2級、宅建
勉強をはじめた時点で、どうせ勉強するなら私の財産にしたいと考えていたので、簿記とFPは2級まで目指すことにしました。
(年表もしくはフロー)
記帳ルールを学ぶ簿記、正確な記憶定着が必要な宅建、暮らしのお金を学べるFP|3つを取得して感じた違い
簿記は世界共通の経済活動のルール。ビジネスにおけるお金の管理について学べます
簿記とは、経済活動を記録・計算・整理し、財務諸表(決算書)を作成するための世界共通のルールです。あらゆるビジネスに役立ちます。
簿記を学ぶことで社会人としてスキルアップを図ることができ、今後のキャリア形成にも役立つだろうと考えました。
また、企業は利益を産み出し発展することを目指し財務諸表を作成しています。簿記を学ぶことは、お金の基礎知識として個人の資産運用やマネープランを検討する上でも役立ちます。これからの人生を考える上での基礎知識にも役立ちます。
簿記の資格試験にはいくつか種類がありましたが、最も一般的な日商簿記を学びました。
日商簿記について、詳しくはこちらの記事をご覧ください(リンク)
宅建は不動産取引の専門家。専門分野を目指したい人にオススメ
宅建とは、不動産売買のプロフェッショナルです。不動産売買の際についての説明や契約書への記名など、宅建士にしかできない業務があります。不動産業を営むには一定割合以上の宅建士を配置する必要があるため不動産業界で働きたいと考える方には有利な資格です。
宅地建物取引士について、詳しくはこちらの記事をご覧ください(リンク)
→宅地建物取引士試験について、詳しくはこちらの記事をご覧ください(記事内に入れる)
FPは暮らしのお金のエキスパート
FPとはファイナンシャルプランナーの略です。ファイナンシャルプランナーとは、暮らしにまつわるお金のエキスパートです。ライフプランに沿った理想の生活に向けたアドバイスを行います。銀行や保険のお仕事では、お客さまへトータルアドバイスが可能となります。その他の会社でも人事部門や総務・経理の必須知識も学ぶことができます。
また、個人のこれからの人生設計を考えるための基礎力となります。
ファイナンシャルプランナー技能士について、詳しくはこちらの記事をご覧ください(リンク)
→ファイナンシャルプランナー技能士試験について、詳しくはこちらの記事をご覧ください(記事内に入れる)
学習の難易度 宅建>簿記>FP|学習を終えた私の感じた体感
- 宅地建物取引士
- 簿記2級
- ファイナンシャルプランナー技能士2級
それぞれ試験の開催頻度や試験の形式などに違いもあり、一概に難易度を比較することは難しいですが、私の考える難易度は宅建、簿記2級、FP2級の順でした。
実際の合格率を比較しても同じ順番になっています。
宅建が一番難しいと感じた理由は、細かな言い回しの違いなどにより正解できない問題があり、知識を正確に丁寧に覚える必要があったからです。
簿記については、基本的な知識を確かめる問題といくつかの知識を土台にしなければ理解が難しい問題があり、特に2級ではそれを感じました。
FPについては、宅建や簿記の知識や考え方が役立つことも多かったため比較的理解しやすかったこともあると思います。
簿記→宅建→FPを受験して感じた学習のコツ|オススメの学習順序
どの資格を先にすると効果的に学習できるか整理してみました。
- 暗記を中心に成功体験を積みあげモチベーションをあげたいならFPを最初に
- 最初の方がやる気があり丁寧に学習を進められると思うなら宅建を最初に
- 新しい概念を学ぶ楽しさを知ることで学習意欲が高まると思うなら簿記を最初に
私は、簿記3級→簿記2級→宅建→FP3級→FP2級の順番で受験しました。
もう一度、受験するとしても、同じ順番で進めます。
その理由は、簿記という新しいジャンルで学ぶ楽しさ、合格する達成感を体験し、学びの習慣がついた上で、宅建という壁にぶつかることができたからです。
宅建という壁を超えたことで、FP2級まで一気に進むことができました。
これは私が久しぶりに試験に挑んだことや、負けず嫌い、嫌なことを先に片付けたいという性格によるところも大きいと思います。
正直、途中に何度かやめてしまおうかと思うこともありましたが、今やらないとこの先に進めないと言い聞かせて、なんとか達成できました。
一般的には、ステップアップ型がオススメされています。
過去に学習経験がない場合は、簿記やFPのように3級、2級と連続して受験する方が理解の上でも暗記する上でも有効でした。
ステップアップの形で進めることで、向かっている方向性の確認ができ、仮に途中で止まってしまっても残るもの(資格)があります。
また、勝ちグセで勢いをつけることもモチベーションアップに繋がりやすいからです。
試験を受験するという場数を踏むことで試験の雰囲気に慣れるということもメリットになります。
結果的に、幅広い知識を身につけることで効果的に仕事に役立てることも可能です。
急がば回れという言葉もあるように、最終的に目標とする資格に一直線に進むよりも周辺知識を学ぶことで結果的に短時間での理解に繋げることも可能となります。
逆に、ステップアップ型で進めることのデメリットとしては、受験期間や費用が余計にかかってしまいます。
本命の前にここでいいかと妥協してしまう可能性があること。途中で失敗してモチベーションが下がることがあること。置かれた状況が変わってしまい諦めざるを得なくなることがあると言ったことも挙げられます。
簿記3級で学ぶ楽しさを知り、簿記2級で成功体験を重ね、宅建で知識の幅を拡げ、身の回りのことを体系的に学ぶFP3級に繋げ、総合力としてFP2級を勝ち取ることができました。
ここまで読んでくださった方なら、もう十分に検討する時間は過ごしているように思います。
いくつの資格を取るか、どの順番で学習しようかと悩んでいても、はじめなければ身につきません。
もし、やってみて、壁にぶつかるなら、どう攻めるか、改めて戦略を立てることも可能です。ここまで書いてきたことに共感できる部分があったなら、私と同じ順番ではじめてみませんか。悩むより、学び始めましょう!